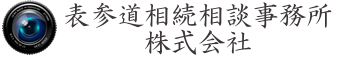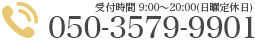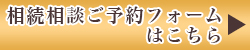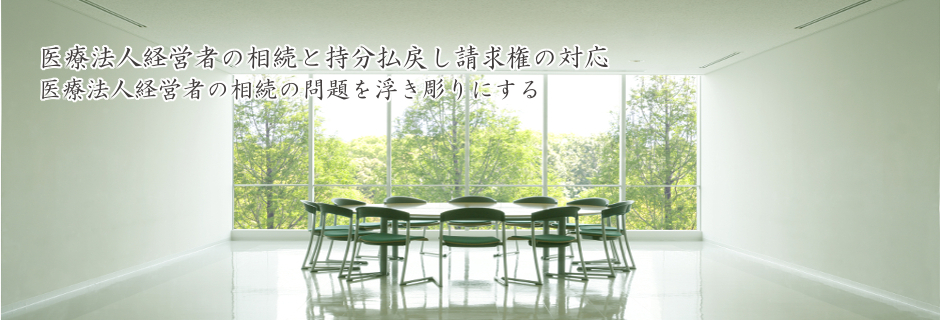医療法人経営者の相続と持分の関係

医療法人経営者の相続には、「持分の対応」と「医療法人経営者の相続」が密接に関わってくるため、双方の問題を円滑に進めることが必要不可欠です。
その中核となる「持分払い戻し請求権」の相続への影響を把握すること、それが、医療法人経営者の相続対策の第一歩と言えます。
持分払い戻し請求権
出資した社員が、その法人を退社する時(社員資格を喪失した時)に、出資した持分の割合に応じて、法人に払い戻しを請求できる権利

- 平成19年3月31日以前に設立された医療法人社団が対象
- 払い戻しを請求された場合、法律上、支払義務が生じる
- 法人の定款第9条或は8条に記載
厚生労働省発行「出資持分のない医療法人への円滑な移行マニュアル」より

具体的な弊害
持分保有社員が退社し、請求権を行使すると、法人の運転資金に大きな影響を及ぼす

→請求者の持ち分所有割合に応じた金額を、法人が払い戻さなければならない
※現在、医療法人の純資産が3億円あり、50%の持ち分を所有する社員が退社した場合、
3億円×50%(1億5000万円)を医療法人に請求できる権利が発生。
持分は相続財産
→持分所有者が持分権利を破棄しない限り、請求権は遺族に引き継がれ、持分は相続財産となる。その場合、法人からスムーズに支払が行えれば良いが、状況により、相続税申告時までに支払が間に合わない場合がある。その場合、それらの資金をどう対応するか?
※相続税の申告は「相続発生後10か月以内」であり、原則、延納は認められない。
後継者が相続する持分権利の相続税と遺産分割資金は準備できているか?
経営権である持分は、事業承継の観点から、後継者が持分を相続し、後継者の経営権をより高めるのが通常であるが、その場合、持分は権利評価財産となり、状況により、相続税と遺産分割用資金に不足が生じるケースがある。それをどう準備するか?
現経営者の資産状況により、該当持分の相続税や遺産分割用資金が十分にあれば良いが、不動産など権利評価財産が多数を占めていると、その納税資金や遺産分割資金が困難となる。
この点が対応・準備出来ているか?
=持分を踏まえた相続財産の診断が出来ているか?
その他、法人経営者の相続への影響
遺留分に抵触した場合、どう対応するか?(持分に対しての遺産分割資金)

遺留分とは法定相続人の内、特定の人物に与えられた「最低限財産を受け取れる金額・割合」
遺留分を行使すると遺言書より効力は上であり、持分も遺留分の対象財産(民法964条及び1028条)
そのため、相続財産の内、一定割合以上を「持分」や「不動産」が占めていると「相続財産を分けられない」という状況が発生する。
法人経営者の総合的な資産状況を踏まえた上で、対応策を講じておかないと、相続税が不足したり、遺産分割がスムーズに行えず、事業承継への影響や法律上の揉め事に発展するケースもある。
法人への影響
・持分所有者への支払資金をどう準備するか?
→持分所有者は勿論のこと、ご遺族にも請求権があるため、その点を考慮せず、訴訟にまで発展するケースが散見される。
持分放棄や出資額限度への変更が困難な理由
持分を放棄すると、他の持分所有者に対し、贈与税(みなし贈与)が発生

→1人が持分を放棄すると、他の持分所有者の持分の評価額が上がるため、その増加分に対して贈与税が課せられる。
※持分を放棄した人の所有額が多ければ、他の持分所有者の贈与税負担が増す
持分所有者全員の放棄は、法人に対して贈与税が課税
→持分の評価金額3000万円超より、最高課税55%が適用。
(持分は原則、法人の純資産から所有割合に応じて価格を算定するため、持分所有者全員が放棄すると、法人の総資産全てを放棄したことになり、法人に対し総資産が贈与されたと見なされる。)
=3000万円以上の持分放棄に対して、最高55%の贈与税が法人に課税される
※法人の資金が一気に減少する上、他の持分所有者が応じるか?という問題
持分の払い戻しを出資額限度に制限する方法もあるが、条件が厳しい
→同族社員の人数、及び、同族の持分所有者の割合が、全体の50%以下が条件
=法人経営者の親族が社員総数の半分を占めていたり、法人経営者の親族の持分総額が全体の50%以上を占めていると制限不可
つまり、現実問題として、持分の払戻しを放棄したり、払い戻し金額を抑えることは不可能に近く、
「持分の資金をどう準備するか?」が1つの課題となっている。
対応策の一例
持分の評価額を抑える
→持分の評価は4つの方法があり、総会の決議を得れば、どの方法を用いても良いとされる。
但し、この4つの評価方法は、それぞれの方法により、倍近く評価額に差が出ることもあり、一番評価額が低い方法で対応することで、法人の払戻金額及び持分所有者の相続税額を下げることが可能。
生命保険を活用し、各種資金を準備する
生命保険は、支払保険料より、受取る死亡保険金の方が多いため、持分所有者の死亡時の払戻し請求権金額の確保、及び、保険の解約金(積立金)を利用し、定年勇退時の払戻し請求権の対応と、同時準備が可能。 法人経営者の相続においては、不足した遺産分割資金や相続税の準備として効果を発揮する。※生命保険独自の非課税枠などもあり
その他の方法
- 遺言信託を活用した対策法(持分を「みなし相続財産」にし、遺産分割協議財産から除外。持分の遺産分割資金を圧縮する)
- 一時的な損金、及び、法人保険を活用し、持分評価額を抑える
持分の対応と法人経営者の相続は一体

持分対応の難しさは、持分の評価と総会で統一の評価方法の決議を得ることです。
当社では、
- 持分評価額の決定までのフォロー
- 医療法人経営者の相続診断、及び、相続税と遺産分割資金の準備
- 持分の対応(法人の支払資金の準備)
医療法人経営者の相続の一助として、是非、当社をご活用ください。
コンサルティング費用

当社の実績・アクセス情報を掲載しています。
詳細はこちら
- 現在は受付停止中
※詳細はお問い合わせください
お申し込みフォーム
フォームからお申し込み後、24時間以内にご連絡をいたします。
入力にあたっての注意事項
- *印は必須です。
- 「面談希望時間帯」の項目は、複数のチェックが可能です。
- フォームの関係上、携帯電話のアドレスは非対応となっております。
御手数ですがPCメールアドレスでご入力頂くようお願い致します。
その他、ご不明点や電話でのお問い合わせ、電話でのお申し込みは、「お問い合わせ先番号」で受付しております。
お問い合わせ先・電話での受付
- メールでのお問い合わせ
-
- メールの場合、24時間受付しています。
- 内容によっては、返信まで最大24時間ほどお時間を頂くことがあります。
- 土日、祝日にご連絡頂いた場合、ご回答が翌月曜日となる場合があります。
- お電話でのお問い合わせ:050-3579-9901
-
- 受付時間9:00~18:00(祝日を除く全日対応)
- お問い合わせ頂く際は「相続のホームページの件で」とお伝え頂くとスムーズです。
- 他の方の面談中など、電話が繋がりにくい場合があります。
その場合は、大変御手数ですが、一時間程時間をおいてから再度おかけ直しください。
表示に関わる備考
- お問い合わせに際し、入力頂いた個人情報は、あくまで本相談の利用のために使用します。
その他目的のために開示、利用する事はありません。 - 掲載している画像は、関係性が構築されているお客様から特別に許可を頂き掲載しています。
如何なる理由があろうとも、画像の無断転載・使用を禁じます。